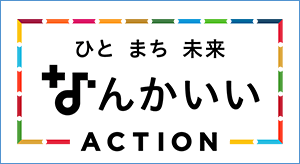質疑応答
分社関係
Q. 分社化によって鉄道事業会社を子会社とした理由は何か。
A. 鉄道とまちづくりの両事業は対等な両輪であるとの認識のもと、事業モデルとして成熟した鉄道事業とは異なり、まちづくり事業はこれから注力分野を見極め、それに適した経営スタイルを確立していく必要があることから、上場会社としてしっかりとガバナンスを効かせることや、人的リソースを十分に割くことが適当であると考えた。まちづくり事業会社が事業持株会社となって、グループ全体の成長をけん引し、鉄道事業に頼らず成長していけるよう、しっかりと取り組んでまいりたい。
鉄道関係
Q. なにわ筋線事業に関する今後の見通しと当社への影響を教えてもらいたい。
A. なにわ筋線事業は、2020年度に事業認可を受け、2021年度から整備主体である関西高速鉄道株式会社において本格着工しており、現在は、2031年の開業に向けて、ほぼすべての区間で工事を行っている状況である。同線が開業すれば、難波駅で乗り換えることなく、大阪・梅田方面に向かうことが可能となり、多くのお客さまの利用が見込まれることから、関係者とともに本事業を着実に進めてまいりたい。
Q. JR西日本との連絡普通乗車券が発売終了となったことは残念である。新今宮駅発売分だけでも残してもらいたい。
A. JR西日本との連絡普通乗車券が発売終了となりご不便をおかけしている点は申し訳ないが、当社では、省資源の観点等から将来的に磁気券を廃止していくとの方針のもと、IC化率の向上に取り組んでいることをご理解賜りたい。
Q. 各駅における電話による問合せ対応を終了したが、主要駅だけでも残してもらいたい。
A. 当社では駅係員の配置の見直しに伴い、2024年6月1日より各駅でのお客さまからの電話による問合せ対応を終了したが、代替として「南海電鉄コールセンター」において一元的に問合せ対応を実施している。「南海電鉄コールセンター」において、従前と変わらない対応を行っているので、ご理解賜りたい。
Q. 大阪市住吉区内の連続立体交差事業について、先月視察に訪れた国土交通大臣にも要望したが、今後、5年から10年の間に、行政による工事準備の採択や都市計画決定がなされる見込みはあるか。
A. 地元の方々の働きかけにより、大阪市が住吉区内における連続立体交差事業の調査を開始したこと、また、国土交通大臣が視察に訪れたことは承知している。これまで当社は、大阪市との情報交換を進めてきており、今年度はボーリング調査や測量の委託を受け実施する予定である。大きな幹線道路と交差しており、連続立体交差事業の採択要件にも合致していることから、当社としても、大阪市と協力して、早期実現に向けて前向きに取り組んでまいりたい。
Q. 大阪市住吉区内の連続立体交差事業について、当社から大阪市側に、単年度ではなく複数年分の予算措置を行うよう働きかけてもらいたい。
A. 連続立体交差事業の予算の立て方は、さまざまな方式があると承知しているが、まずは国から着工準備についての採択を得られることが先決であり、ご理解賜りたい。
Q. インバウンド旅客向けの乗車マナーの啓発や、車内混雑緩和策を教えてもらいたい。
A. 車内にマナー啓発ポスターを掲出するほか、特急ラピートにおいてチラシを配布するなど、さまざまな取組みを行っているが、まだまだ十分ではないと認識している。インバウンド旅客のさらなる増加を見据え、今後ともマナー啓発活動をより一層強化してまいりたい。また、物理的な対策として、難波駅と関西空港駅において、スーツケース等の大きな手荷物の一時預かりやホテルへの配送を行うサービスを手掛けているので、車内への持込みを減らせるよう取り組んでまいりたい。
不動産・まちづくり関係
Q. 不動産事業の飛躍的拡大を掲げて取り組んでいくとのことだが、不動産事業のリスクについては、どのように考えているのか。
A. 沿線・長期保有中心の従来の枠組みでは、エリア・アセットが限定され成長は頭打ちであることから、不動産事業のリスクを踏まえつつ、事業エリアの拡充とスキームの多様化により、新たな収益機会の創出に挑戦していく必要があると考えている。不動産事業のノウハウを有する社員もキャリア採用等を通じ増えており、将来の成長に寄与するビジネスモデルへと進化させてまいりたい。
Q. なにわ筋線事業の完成に伴い、なんばエリアが通過点になってしまうことが懸念されるため、当社が株式会社髙島屋や、本社移転後の跡地活用を計画する株式会社クボタ等をリードして、なんばのまちを成長させてもらいたい。
A. 「南海グループ経営ビジョン2027」において、「なにわ筋線開業に向け、沿線を磨く10年間」と位置付け、2018年には「なんばスカイオ」を開業させるなど、沿線、とりわけなんばエリアの価値向上に取り組んできた。現在、インバウンド旅客を中心に多くの方々に来訪いただいており、国際観光都市としての発展と都市機能の充実を両立させながら、なんばターミナルから新今宮、新世界へと続く南北ラインを軸に、賑わいのある回遊空間を創出し、より魅力的でわくわくするエリアへと進化させていきたい。その一環として、昨年12月に当社グループに加わった「通天閣」との連携を行うなど、エリア価値の向上に一層努めてまいりたい。
Q. 大阪市住吉区内の連続立体交差事業が完成した後は、その高架下部分において、地域と一体となった開発を行い活性化させてもらいたい。
A. 既に連続立体交差事業が完成した他の区間の高架下においては、各地域の特性やニーズに応じた開発を行っており、本区間においても、高架化が実現すれば検討してまいりたい。
経営戦略関係
Q. 業績好調で新たな中期経営計画を公表した中、株価が右肩下がりになっている原因と対策について教えてもらいたい。
A. 株価はさまざまな要因で変動するものとはいえ、足元では株主の皆さまの期待に沿えていないことは遺憾である。当社グループでは、多くの成長の種があり、「NANKAIグループ中期経営計画 2025-2027」では、こうした成長の種をもとに不動産事業の飛躍的拡大等、大きな成長を志向する企業体への変革に取り組んでいく。また、今年度は、大きな成長に向けて集中的に投資を行うため、減益予想となっているが、業績管理にROICを活用するなど、資本効率性の向上に取り組むことで、株価としっかりと向き合ってまいりたい。また、IR活動にも注力して、投資家との対話にも努めてまいりたい。
総務関係
Q. 株主総会会場を変更したことでコスト削減につながったのではないか。
A. 昨年、株主総会会場として使用した大阪府立体育会館においては、施設の老朽化に伴う大規模改修工事が実施され、使用できないことから本会場での開催に至ったが、費用面では従前と比べ大きくは変わらない。
Q. 株主総会会場変更に伴うコスト削減分を、例えばお土産を配るなどして、株主に還元してもらえないか。
A. かつて、当社では株主総会に出席された株主の皆さまにお土産をお渡ししていたが、コロナ禍を経てバーチャル総会を行う会社も徐々に増えつつあり、将来的に一般的になることが見込まれる中において、会場にご来場された方にのみお土産をお渡しすることは、公平さを欠くことになると考えている。ご来場された方への感謝の気持ちに変わりはないが、今後もお土産のお渡しは取りやめを継続させてもらいたい。
グループ会社関係
Q. 消滅可能性自治体に指定されたエリアに住んでいるが、AIオンデマンドバスやグリーンスローモビリティ等、公共交通の維持に向けた取組みは、具体的にいつ実現できる見込みなのか。
A. 人口減少は日本全国が抱える課題であり、当社としてもAIオンデマンドバスやグリーンスローモビリティ等、さまざまな実証実験を行っているが、どれも実験段階である。担い手やコスト面等で解決すべき課題が多いが、公共交通維持に向けて取り組んでまいりたい。
その他
Q. 近時の当社取組みから、社長には前向きに頑張ろうとする意志がうかがえる。引き続きその姿勢で各施策に取り組んでもらいたい。
A. 当社に対する𠮟咤激励のご意見であり、しっかりと受け止め、今後の各種取組みや施策につなげてまいりたい。
ホームページで受けた質問について
Q. 駅のホーム上の時刻表がなくなり、QRコードを読み取る方式に変わっているが、利用者にとって優しくない。従来の時刻表を駅に復活させてもらいたい。
A. スマートフォン等のデジタル媒体の普及から、リアルタイムで列車運行状況等をお手許で確認できるよう、掲示物のデジタル化を進めており、時刻表のQR化もこの一環である。今後とも、お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、誰もが利用しやすい情報提供を検討してまいりたい。なお、駅係員にお申し出いただければ、紙の時刻表をお渡ししているので、お声がけ賜りたい。
Q. 空き状況が目立つが、泉北ライナーの見直しは検討していないのか。
A. 泉北ライナーについて、平日朝の上り列車や夕方以降の下り列車では、一定のご利用があるものの、全体的には利用状況が低調である。特に土休日ダイヤにおいては、乗車率が低い傾向にあり、今後、ご利用の少ない列車は発着時刻の見直しやさまざまな営業施策を通じて、より多くのお客さまにご利用いただけるよう取り組んでまいりたい。
Q. 高野線大阪市内の連続立体交差事業について、沢ノ町駅と我孫子前駅を統合して両駅の中間に「住吉中央駅(仮称)」として整備してほしい。
A. 高野線大阪市内の連続立体交差事業については、都市計画立案に向けての調査段階であり、事業主体となる大阪市では、地元による署名活動等を受けて、2021年度から調査・検討を始めたと聞いている。当社では、駅の新設は検討していないが、大阪市と積極的にコミュニケーションをはかり、連続立体交差事業計画が具体化されるよう協力してまいりたい。
Q. 優先座席の利用マナーが守られるよう、自動放送の頻度を高める、英語で放送する、優先座席の案内を増やすなどの取組みをしてもらいたい。
A. 優先座席の利用マナーについては、駅構内・車内放送を通じてご協力をお願いしており、日本語のほか、英語・中国語・韓国語にて実施している。車内では、座席シートの色分けによる明示をはじめ、窓ステッカー及びつり革への優先座席の案内表示を行っているが、今後の新造車両においては床面への案内表示の掲出を予定している。
Q. 列車行先案内表示装置について、主要駅以外にも設置してもらいたい。
A. 次列車の案内を行う「列車行先案内表示装置」は、主要駅以外の駅では列車案内情報の送受信システムが構築できていないため、現在のところ主要駅のみの設置となっている。なお、列車の在線情報については、「南海アプリ」にてリアルタイムで配信しているので、アプリのご利用をご検討いただきたい。
Q. 列車識別灯が、夜に眩しいと感じるため、明るさを落してもらいたい。
A. 「列車識別灯」は、LED化に伴い以前よりも明るくなっているが、線路上で作業する工事関係者に対しても列車種別をお知らせするために安全上必要な設備であり、ご理解賜りたい。
Q. 泉北高速鉄道の車両デザインや意匠は残してもらいたい。
A. 合併に伴い、企業ブランドの一体化や企業文化の融合をはかることを目的として、順次、当社仕様への統一を進めているが、統一までは相当な期間を要するため、当社と泉北高速鉄道の車両デザインが当面の間は混在することになる。これまでのデザイン等への愛着や要望の声を真摯に受け止め、仕様統一後についても、イベント等の機会を通じて、従来のデザインを活用することを検討してまいりたい。
Q. 10000系サザンの復刻塗装車両の運行について、4両単独で運転してもらいたい。また、一度限りにせず、複数回運行してもらいたい。
A. 10000系サザンの復刻塗装車両の運行について、現在のところ臨時列車を含めて4両単独での運用予定はないが、今後のイベント等における車両運用の参考とさせていただく。
Q. 新型車両のデザインを決める際は、複数案を候補として、投票制で決めてもらいたい。
A. 今後の車両設計の参考とさせていただく。
Q. 特急サザン乗車時、泉佐野駅からみさき公園駅間で横揺れが激しいように感じるが原因は何か。
A. 線路は、通過する列車の衝撃等によりゆがみが発生し、一般的に横揺れが発生する箇所は、レールの横方向のゆがみが原因となっていることが多い。そのため当社では、定期的に検査を実施して数値管理を行い、ゆがみが大きい箇所については、補修計画に基づき随時補修を実施して対応している。
Q. インバウンド旅客がスーツケース等の大きな手荷物を持って乗車された場合、高野山ケーブルカーの車内が狭く、ホーム上も急な階段で不便である。また、鉄道事業の分社化後は、東京証券取引所の「業種分類」が「陸運」から他に変更されるのか。
A. 高野山ケーブルカーでは、現在、エレベーターの設置等により動線の改善をはかっているほか、多客時には臨時便の運行を行い、分散乗車による混雑緩和に努めている。
また、東京証券取引所における当社の「業種分類」は、証券コード協会が策定した「業種別分類に関する取扱い要領」という判定基準に基づき、東京証券取引所が判定し公開しているものである。このため、変更の有無は、同取引所が判定することになるが、同要領を見る限り「親会社単体の事業でなく、子会社を含めた連結全体として判定するもの」とされており、分社化により「業種分類」の変更はないものと認識している。
Q. 鉄道事業の分社後も現状の株主優待制度に変更はないか。
A. 鉄道事業の分社化に伴う株主優待制度の変更の予定はないが、株主の皆さまにとって魅力ある株主優待制度となるよう、今後もさまざまな視点から検討を続けてまいりたい。
Q. 業績に対して株価が低迷しているが、今後の株価対策の方針を教えてもらいたい。
A. 株価はさまざまな要因で変動するものとはいえ、足元では株主の皆さまの期待に沿えていないことは遺憾である。当社グループでは、多くの成長の種があり、「NANKAIグループ中期経営計画 2025-2027」では、こうした成長の種をもとに不動産事業の飛躍的拡大等、大きな成長を志向する企業体への変革に取り組んでいく。また、今年度は、大きな成長に向けて集中的に投資を行うため、減益予想となっているが、業績管理にROICを活用するなど、資本効率性の向上に取り組むことで、株価としっかりと向き合ってまいりたい。また、IR活動にも注力して、投資家との対話にも努めてまいりたい。
Q. 「NANKAIグループ中期経営計画 2025-2027」にある「未来探索」とは、具体的にどのような取組みを指すか。
A. 南海が描く“2050 年の企業像”に向かって企業価値の大きな向上を実現するにあたり、現状の2つのコア事業である不動産事業及び・公共交通事業を強化していくことに加えて、新たな事業分野を探索し育成することが必要と認識しており、これを「未来探索」と表現している。
具体的には、eスポーツ事業・ツーリズム事業を一定の規模に成長する可能性のある事業と認識しており、経営資源を投入してスケールアップをめざしてまいりたい。また、それ以外の分野についても、M&AやCVC(スタートアップ企業への投資活動)を有効活用しながら、成長性と収益性のポテンシャルを有する事業モデルの探索と深掘りを積極的に行い、可能性の高い事業に集中的にリソースを投入してまいりたい。
Q. 南海トラフ地震に備えた鉄道施設の耐震対策が中期経営計画に明記されていない理由を教えてもらいたい。
A. 南海トラフ地震は、発生時に当社グループの経営に与える影響が甚大であることから、優先・継続して対策に取り組むべきリスクであると認識しており、「NANKAIグループ中期経営計画 2025-2027」の資料24ページ「安全・安心・信頼の提供、災害対策」では、南海トラフ地震をはじめ、直下型地震や豪雨・暴風などのリスクも包含する形で「激甚化する災害への対策を実行」と記載している。
現中期経営計画期間は、コア事業の強化(集中投資)を最優先し、公共交通事業への変革に向けて最大1,300億円の投資を実行するが、鉄道施設の耐震補強は、南海トラフ地震の発生も考慮した国が定めた省令に基づき、整備を進めているところである。駅舎や高架橋、橋りょうの補強をはじめ、各種防災対策等にも、集中的に投資を実行する計画である。